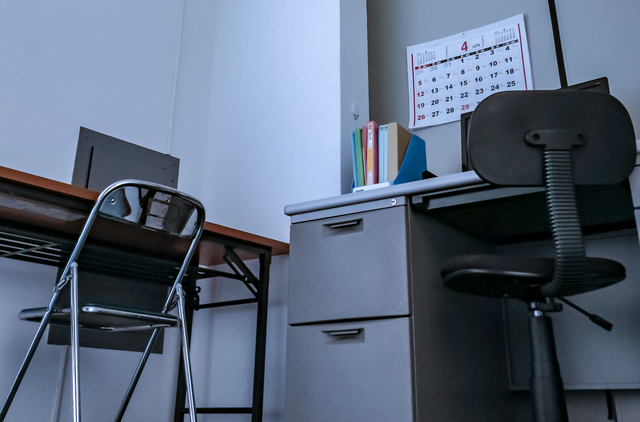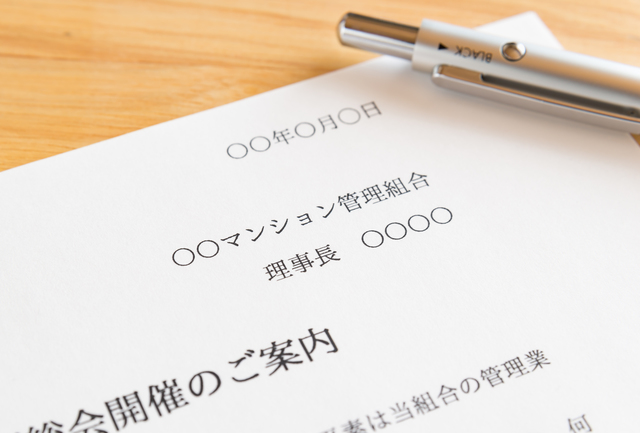区分所有法では、集会は管理者が招集するとされています(区分所有法34条1項)。
また、標準管理規約では、
- 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない
- 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる
とされています(標準管理規約3項・4項)。
したがって、総会は原則として理事長が招集することになります。
もっとも、区分所有者が総会を招集したり、理事長に対して総会の招集を請求できる場合もあります。
区分所有者による総会の招集は、①管理組合が法人の場合、②管理組合が法人ではないが管理者がいる場合、③管理組合が法人でなく管理者もいない場合、の3つの場合により手続きが異なります。
①管理組合が法人の場合・②管理組合が法人ではないが管理者がいる場合
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者[管理組合法人の場合は理事]に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができます(区分所有法34条3項本文、47条12項)。
定数
区分所有者の(人数の)5分の1以上、議決権の5分の1以上という定数は、規約で引き下げることができますが(区分所有法34条3項但書)、規約で引き上げることはできません。
標準管理規約44条1項は、組合員が、組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない、としています。
この点、組合員の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者の同意さえ得ていれば、組合員が単独で総会の招集を請求することができるとする規約は無効であるとしながら、同意した組合員の代理人として1人の組合員が招集請求をしたものと解することができる限りは有効であるとした裁判例があります(東京地裁平成23年9月28日)。
<東京地裁平成23年9月28日>
法34条3項は、…集会の招集請求をした区分所有者が、全区分所有者の5分の1以上であり、かつ、議決権の5分の1以上を有する者であることを前提にしているものと解される。
これに対し、本件規約…は、「組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上にあたる組合員の同意を得て総会の招集を請求した場合」と定めており、文字通り読めば、総会の招集を請求する組合員が組合員の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者である必要はなく、組合員の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者の同意さえ得ていれば、組合員が単独で総会の招集を請求することもできるかのような規定となっている。
そこで、まず、そのような趣旨の規約を定めることが許されるかどうかが問題となるところ、法34条の規定は、その性質上強行規定と解すべきであるから、明文で認められている区分所有者の定数を除き、その要件を緩和することは許されないと解すべきである。
また、実質的に見ても、仮に上記のような趣旨の規約を有効とすると、招集請求を受けた理事長あるいは招集通知を受けた組合員において、組合員の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者の同意を得た有効な招集請求あるいは招集通知であるかどうかを判断することが著しく困難となり、相当でない。
そうすると、本件規約…を、組合員の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者の同意さえ得ていれば、組合員が単独で総会の招集を請求することができる旨の規定と解するのであれば、そのような規定は無効といわざるをえない。
もっとも、法34条3項も、区分所有者が、他の区分所有者を代理人として招集請求をすることまで禁止しているとは解されないところ、招集請求自体は1人の組合員名で行われたとしても、これに同意した者の氏名が招集請求書に明記されるなど、同意した組合員の氏名が招集請求自体から明らかである場合には、実質的にはこれらの組合員の代理人として1人の組合員が招集請求をしたものと解することができる。
本件規約…も、そのような方法による招集請求を許容した規定と解釈することが可能であり、また、そのように解釈する限りにおいては、有効と考えられる。
総会の招集請求
総会の招集を請求する方法は、管理者[理事長]が定数の要件をみたすものであると判断できるものである必要があります。
この点、以下のような裁判例があります。
- 集会招集請求を受けた管理者としては、当該請求が外形上要件を満たした適法なものかどうかを認識し、当該請求を受けて自ら招集の通知を発するのか否か、その後の当該区分所有者がした集会招集が適法なものであるか否かを検討することができる必要があるというべきであるから、当該請求は、頭数要件及び議決権比率要件を満たす具体的な区分所有者によるものであることを示してされることを要する(東京地裁平成22年2月3日)
- 組合員が総会を招集するに当たっては、規約に定める総数要件及び議決権要件を充足することが必要であることはもとより、理事長に対し、組合員からされた総会の招集請求がこれらの要件を充足しているか否かを判断することが可能な程度の資料・根拠を提出するか又はその閲覧の機会を与える必要がある(東京地裁平成25年5月27日)
<東京地裁平成22年2月3日>
管理者が集会の第1次的な招集権を有し…[区分所有法34条1項]、少なくとも毎年1回集会を招集する義務を負う…[区分所有法34条2項]とした上で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理のため、ないしは区分所有者の利益を適正に保護するために、前記頭数要件及び議決権比率要件を満たした区分所有者に対し、固有の集会招集請求権を認め、さらに、裁判所の許可の手続などを要することなく当該区分所有者が集会を招集できるとしたものであるが、この集会招集請求を受けた管理者としては、当該請求が外形上上記要件を満たした適法なものかどうかを認識し、当該請求を受けて自ら招集の通知を発するのか否か、その後の当該区分所有者がした集会招集が適法なものであるか否かを検討することができる必要があるというべきであるから、当該請求は、前記頭数要件及び議決権比率要件を満たす具体的な区分所有者によるものであることを示してされることを要すると解すべきである。
また、…本件管理規約は、組合員の総会招集権について、前記頭数要件及び議決権比率を満たした組合員の同意を得た組合員が会議の目的を示して総会の招集を請求した場合に、理事長は臨時総会の招集の通知を発しなければならない旨規定し…、理事長がその通知を発しない場合には、当該請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる旨規定している…ことが認められるが、前記の区分所有法34条3項の趣旨からすれば、本件管理規約…について、当該請求は、外形上前記頭数要件及び議決権比率要件を満たした具体的な組合員の同意を得た組合員(当該請求をした組合員自身を頭数要件の頭数に入れること及び同組合員の議決権を議決権比率要件の議決権に入れることができると解される。)によるものであることを示してされることを要すると解すべきである(なお、同条は、総会招集権者に関し、区分所有法34条3項と異なり組合員が単独で行うとしているが、それ自体が同項に違反し無効であると解すべきではない。)。
しかるに、本件招集請求は、…Aが、組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得たとして、Aが単独でするものであり、本件招集請求が前記頭数要件及び議決権比率要件を満たした具体的な組合員の同意を得てされたものであることが示されていないから、本件招集請求は、本件管理規約…に反する瑕疵があり違法である。
…この点、被告は、本件招集請求に請求者らの表示がないことが違法だとしても、形式的な瑕疵であり、組合員数25名、議決件数50票の絶対過半数を超える賛成でされた本件臨時総会決議を無効とする実質的な違法性はないと主張する。
…本件招集請求当時の被告の全組合員数は46、全議決権数は71であること…、…Aを含む被告の19名の組合員において、当時の理事長であった原告にあてて、…役員の選出等の本件招集に係る集会招集請求書と同一の事項を会議の目的とする集会招集請求書を作成していることが認められ、これによれば、本件招集請求については、前記頭数要件及び議決権比率要件を実質的に満たしていることになるが、…これら19通の集会招集請求書は原告に送られていないことが認められ、他に、本件招集請求について、これが適法にされたものであることを原告が認識できるような態様でされたことを認めるに足りる証拠がないことからすれば、本件招集請求の瑕疵が軽微であり、本件臨時総会決議を無効にするだけの実質的な違法性がないとはいえない…。
<東京地裁平成25年5月27日>
建物の区分所有等に関する法律34条は、区分所有建物(マンション)における総会の第1次的招集権者をその団体の事務執行者である管理者(本件マンションにおいては理事長)と定め(同条1項)、一定数以上の区分所有者が総会の招集を希望する場合であっても、まずは管理者に対して総会の招集を請求させ、管理者において、同請求権の有無を確認した上、総会招集手続をとらせることとした(同条3項)のであるから、この趣旨からすると、組合員が総会を招集するに当たっては、本件管理規約41条1項に定める総数要件及び議決権要件を充足することが必要であることはもとより、理事長に対し、組合員からされた総会の招集請求がこれらの要件を充足しているか否かを判断することが可能な程度の資料・根拠を提出するか又はその閲覧の機会を与える必要があると解するのが相当である。
…以上を前提に、本件について検討するに、…被告Y2がX1理事長に対し、臨時総会招集請求書(本件同意書が添付されていないもの)を交付した後、被告Y4が、ファイルに綴られた本件同意書…を手に持ったまま、その上部に記載された議題を読み上げた上、4枚からなる本件同意者を1枚ずつ提示したこと、これに対し、X1理事長は本件同意書を交付するよう要求したが、被告Y4が個人情報であるので渡せない旨述べてこれに応じなかったこと、被告Y4がX1理事長に本件同意書を提示した時間は、長くても、1枚目が15ないし20秒、その余は1枚当たり10秒程度であったことが認められ、その間、X1理事長は本件同意者に署名・押印した者の氏名を一人ひとり確認したり、メモをとったりする状況にはなかったものというべきであるから、これらの事情に徴すると、本件においては、X1理事長に対し、臨時総会の招集請求が本件管理規約41条1項に定める総数要件及び議決権要件を充足しているか否かを判断することが可能な程度の資料・根拠が提出されず、かつ、その閲覧の機会も付与されなかったというほかはない。
したがって、本件臨時総会の招集請求手続には重大な瑕疵がある。
…もっとも、上記のとおり、本件臨時総会の招集請求手続には重大な瑕疵があるとはいえ、…被告らの主張する本件臨時総会は、平成24年1月15日午後7時ころから午後9時ころまでの間開催され、26人が出席したこと、有効出席数は、議決権行使書により議決権を行使した者29人及び本件臨時総会の請求人である被告Y2に議決権行使を白紙委任した者45人を併せ100人であったため、定足数を満たしているものとして議事が進められて、外形的には、X1理事長解任総会決議や新理事等選任総会決議がされたことが認められるから、これらの事情に徴すると、本件臨時総会自体及びそこにおける各決議が不存在であると認めることはできない。
…本件臨時総会の招集請求手続には重大な瑕疵があるというべきであるから、X1理事長が同請求に応じないことを理由として招集された本件臨時総会並びにそこにおけるX1理事長解任総会決議及び新理事等選任総会決議には重大な瑕疵があり、いずれも無効であるというべきである。
…また、新理事等選任総会決議が無効である以上、新理事長選任理事会決議は、無効な選任決議によりその地位に就いた理事によってされたものであるから、無効というほかはない。
総会招集の請求の要件に関して、「管理者は、…請求が適正になされていることを請求者全員の実印の押印(印鑑登録証明書を添付)により確認を行わなければならない。」という規約の記載があり、実印の押印や印鑑証明書の提出等を必要とする事例がありますが、国交省の「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」(令和6年6月)には、マンション管理業者による外部管理者方式(管理業者管理者方式)における留意事項として、以下のような記載があります(90頁)。
管理組合によっては、総会招集の請求が区分所有者本人によって適正に行われていることを管理者が確認するため、特定の公的書面を要求する管理規約を定めている事例があります。組合員による総会招集を実質的に困難にする可能性がある要件を規定するかどうかについて、その必要性があるのか、そのような規定を設ける前において、管理者と管理組合との間で十分に協議するべきと考えられますし、そのような規定を設けている場合においても、その必要性について十分に検討するべきと考えられます。
また、マンション管理センターの「予備認定基準(令和7年2月1日基準)における追加基準項目に関する事務運用指針」(令和6年10月31日)においても、『5分の1よりも引き上げた議決要件を規定したり、他の手続きを加えること等により組合員による総会招集を実質困難にする可能性のある要件を規定して、組合員の総会招集権を制限したりすることは、強行規定である「建物の区分所有等に関する法律」第34条第3項等の規定に反し、無効であることに留意すること。』とされており(6頁)、留意が必要です。
総会の招集
区分所有者による総会の招集請求がされた場合において、2週間以内に、その請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかったときは、総会の招集請求をした区分所有者は、集会を招集することができます(区分所有法34条4項)。
標準管理規約では、理事長が通知を発しない場合には、総会の招集を請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる(44条2項)、とされています。
日・週・月・年によって期間を定めた場合、期間の初日は算入されないため(民法140条本文)、請求の日から「2週間以内」・「4週間以内」とは、請求をした日の翌日から2週間以内・4週間以内という意味です。
この点、管理者[理事]が、2週間以内に招集の通知を発したとしても、集会の会日が4週間経過後の日であるときは、総会の招集をした区分所有者は、4週間以内の日を会日とする総会を招集できると考えられます。
他方、管理者[理事]が、2週間以内に招集の通知を発しなかったとしても、4週間以内の日を会日とする招集の通知を発した場合、総会の招集を請求した区分所有者は、総会を招集できないと考えられます。
また、請求の日から2週間が経過する前であっても、その前に管理者[理事]から招集しないとの回答があれば、総会の招集を請求した区分所有者は、直ちに総会を招集することができると考えられます。
③管理組合が法人でなく管理者もいない場合
管理組合が法人でなく管理者がいない場合、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、連名で集会を招集することができます(区分所有法34条5項本文)。
管理者がいない場合、管理者が選任されていない場合や管理者が欠けている場合をいいます。
区分所有者の(人数の)5分の1以上、議決権の5分の1以上という定数は、規約で引き下げることができますが(区分所有法34条5項但書)、規約で引き上げることはできません。
この点、任期満了により退任した前理事長に対する総会開催の請求をすることなく総会を招集をした場合、総会の決議は無効であるとした裁判例があります(東京地裁平成24年3月19日)。
<東京地裁平成24年3月19日>
原告は、この際に理事による互選によって管理者たる理事長が選任されていないため、その後に行われたB[区分所有者]による…の臨時総会の招集は区分所有法34条5項に基づき適法にされたと主張する。
しかし、仮に互選による理事長の選任がされていないとすれば、原告の管理規約…の、「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。」との規定…により、任期満了により退任した前理事長である被告Y1が後任理事長就任までの間引き続きその職務を行うこととなるから、同人が管理者となるというべきである。
よって、Bが、…総会を、区分所有法34条5項の管理者がないときの手続により招集したのは前提を欠くものであって有効な招集手続たり得ず、当該総会における決議は無効である。
…以上によれば、…理事の互選により原告の理事長が選任されていないという原告の主張を前提としても、Bの行った臨時総会招集手続は有効なものではないから、…臨時総会で行われた決議は無効であり、これを前提として行われたことが明らかなその後の臨時総会等での決議も無効である。
原告は、…以後の総会における組合員の意思の積み重ねにより瑕疵が治癒されたとするが、組合員全員が出席した総会による決議等があれば格別、そのような事情は認められないから採用できない。
加えて、原告は、本件確認書を大部分の組合員から取り付けたので、役員選任手続に瑕疵があったとしても治癒されていると主張するが、このような手続で総会決議の瑕疵を治癒することができないのは明らかであるから、およそ採用できない。
また、原告は、…被告Y1が理事に選任されて以降、3年以上にわたって、総会の招集手続等をしていないことをもって、被告らが原告の役員選任の手続の瑕疵を主張することは信義則違反であるとするが、…信義則違反とすべき事情があるとは認められない。